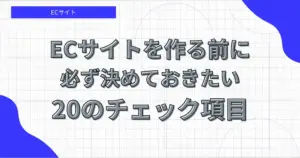ECを始めたいけど、「ShopifyとMakeshop、どっちが自社に合うの?」と迷っていませんか?両者はどちらも実績のあるサービスですが、得意領域や料金体系、サポートの渡し方がかなり違います。ここでは中小企業の経営者や担当者向けに、初心者にもわかりやすく、しかも実務で使える観点で比較していきます。
まずは「ざっくりどんな違いがあるか」を掴んで、そのあとで具体的な料金や機能の比較表、サポート面・拡張性の違い、最後に「自社ならどっち?」を判断するためのポイントをお伝えします。読み終わるころには、無料トライアルで試すべき候補が明確になりますよ。

1. ShopifyとMakeshopの基本概要|まず知っておきたい特徴
ECプラットフォームを選ぶとき、最初に気になるのは「誰向けのサービスか」「どこまで拡張できるか」「国内向けか海外向けか」といった基本的なポイントです。これを押さえておくと、自社に合ったサービスを判断しやすくなります。そこで、ShopifyとMakeshopの特徴を比較表で整理しました。
| 項目 | Shopify | Makeshop |
|---|---|---|
| 提供会社 | Shopify Inc.(カナダ) | GMOメイクショップ株式会社(日本) |
| サービス形態 | クラウド型(多言語・多通貨・アプリ拡張が豊富) | ASP型(日本市場向けの機能が充実、国内決済や配送に強い) |
| 得意領域 | 越境EC・スケールしやすいEC全般 | 国内販売、中小〜中堅向けの現場サポート |
| 導入のしやすさ | テンプレートやアプリで短時間導入可 | 国内向けの管理画面で日本語サポート充実 |
ポイントは、Shopifyは拡張性と海外展開に強く、Makeshopは日本市場に寄り添った安心感が強いということ。これだけだとまだ判断できないので、次は料金と機能を細かく見ていきましょう。
2. 料金比較:初期費用・月額・手数料を詳しく見る
料金は選定で最重要のひとつです。「初期費用が安い=トータルで安い」とは限らないので、月額だけでなく決済手数料や外部アプリの費用、売上が伸びた時のスケールコストも見ておきましょう。
| 比較項目 | Shopify(目安) | Makeshop(目安) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円(テーマ導入や外部制作は別途) | 11,000円(税込)〜(プランによる) |
| 月額費用 | 約4,750円(Basicプラン)〜39,800円程度(上位) | 約12,100円〜(プランにより大幅変動) |
| 決済手数料 | Shopify Paymentsで約3.25%〜(国・プランで変動) | 決済会社によるが3.14%〜(選択肢と契約条件で変動) |
| 追加アプリ費用 | 無料〜月数千円〜数万円(導入するアプリ次第) | 標準機能が豊富な分、外部連携は抑えられる場合あり |
| 越境(多通貨)コスト | 多通貨対応がしやすいが決済手数料や為替コストあり | 基本は国内向け。越境は追加設定や別サービス検討が必要 |
補足しておきたいのは、初期費用が安く見えても実際の運用コストは異なるという点です。Shopifyは基本プラン自体は手頃ですが、デザインや機能を自社に合わせると追加アプリや外部依頼が必要になり、結果的に費用がふくらむことがあります。一方、Makeshopは月額料金がやや高めですが、国内向けの機能が最初から整っているため、追加費用を抑えやすい傾向があります。
つまり、料金の見え方だけで判断するのではなく、自社に必要な機能をどこまで標準でカバーできるか、後から追加コストがどのくらい発生しそうかをイメージすると選びやすくなります。
3. 機能比較:デザイン自由度・決済・アプリ連携・SEOなど
料金の次は機能です。初心者の方ほど「最初から全部揃ってると安心」という気持ちになりますが、将来的な拡張を見越すと「柔軟に足せるか」も大切です。以下の表は、実務でよく比較されるポイントを並べています。
| 機能 | Shopify | Makeshop |
|---|---|---|
| デザインテンプレート | 豊富(公式・サードパーティ多数)、カスタマイズ自由度高い | 国内向けテンプレ多数、管理画面で使いやすい |
| 決済方法 | 多通貨・多決済に対応(Shopify Payments推奨) | 国内決済(コンビニ、キャリア決済等)対応が充実 |
| アプリ/拡張性 | App Storeで数千のアプリ、機能追加が容易 | 標準機能が豊富だが、外部アプリは限定的 |
| 多言語・越境対応 | 強力(多言語・多通貨・海外配送連携がしやすい) | 基本は国内向け。越境が必要なら追加検討 |
| SEO関連機能 | URL構造やメタ情報の制御が可能。アプリで強化可 | 基本的なSEO設定は可能。内部構造は国内向け最適化 |
| 在庫・受注管理 | 外部連携やアプリで高度な運用が可能 | 管理画面で日本の業務フローに合う設計 |
| 配送・物流連携 | 多様な物流サービスと連携可能(海外配送も) | 国内配送会社との連携がスムーズ |
補足すると、Shopifyは「後から足す」ことでどんどん拡張できるのが魅力です。逆にMakeshopは「最初からほしい機能が揃っている」ため、カスタマイズの手間を減らしたい企業には向いています。
4. サポートと運用体制の違い
サポート体制は、特にEC初心者にとって決定的に重要です。実際に何が違うのか、ざっくりまとめます。
- Shopify:オンラインヘルプやコミュニティが充実。日本語サポートはあるが、時間帯や対応範囲に差がある場合あり。
- Makeshop:国内サポートが手厚く、電話対応や導入支援が充実しているプランもある。ローカルな商習慣にも詳しい。
実務目線では、「海外展開を視野に入れるか」「国内のきめ細かいサポートが欲しいか」で選び分けると良いです。特に非エンジニアの担当者が運用する場合、Makeshopのサポートは心強いケースが多いです。
5. どんな企業に向いているか(実務的な選び方)
ここまでを踏まえて、実務での選び方を整理します。自社の状況に合わせて優先順位をつけてください。
- Shopifyがおすすめなケース:将来的に海外展開をしたい、豊富な外部アプリで機能を追加したい、スケールを前提に柔軟に作り込みたい企業。
- Makeshopがおすすめなケース:国内中心の販売、国内決済や配送の手続きが優先、導入後の日本語サポートや運用支援を重視する企業。
迷ったときは、まず無料トライアルやデモで実際に管理画面を触ってみるのがおすすめです。感覚的に「操作しやすい」「管理が楽」と感じる方に軍配が上がることが多いです。
6. 実務で失敗しないためのチェックポイント
導入前に押さえておきたい具体的なチェック項目を挙げます。ここを確認しておくと、導入後の手戻りが減ります。
- 希望する決済手段が標準で使えるか(例:コンビニ、代引、クレジット、キャリア決済)
- 送料や送り先のルール設定が柔軟にできるか
- 将来的に多言語や海外販売をする可能性があるか
- 管理画面の操作性(担当者が使いやすいか)
- サポートの体制(電話対応・メール・導入支援)
これらをチェックリストとして実際に照らし合わせると、どちらのサービスが自社に合うかがはっきりします。
まとめ:まずは目的をはっきりさせて試してみよう
結論としては、「何を重視するか」で選び方が変わります。拡張性や越境を重視するならShopify、国内運用の手厚さや初期導入の安心感を重視するならMakeshopが候補です。
まずは無料トライアルで管理画面を触り、上で挙げたチェックポイントを実際に確認してみましょう。もし「どちらがいいか迷う」「自社の要件を整理してほしい」という場合は、無料相談で専門家に相談するのが近道です。実際の売上目標や業務フローを元に、最適な選択肢を一緒に整理します。
ホームページリニューアル.comでは、中小企業向けのホームページ改善・リニューアルに関して、契約不要の無料相談を受け付けています。
まずはご相談いただき、現状を整理するところから始めてみてください。もちろん相談だけでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
\ 話を聞くだけでもOK。無理な勧誘はありません。 /