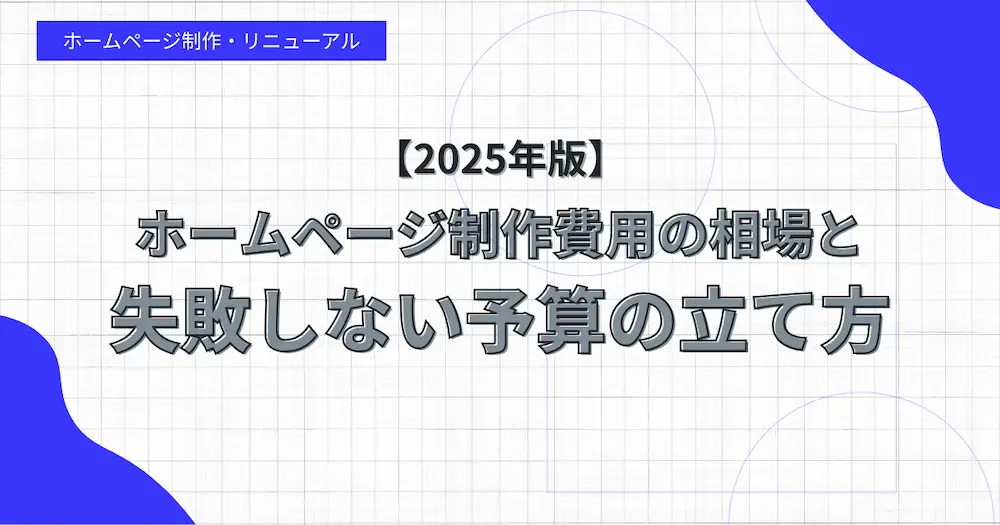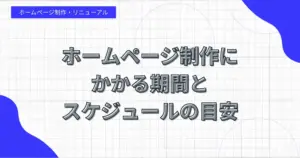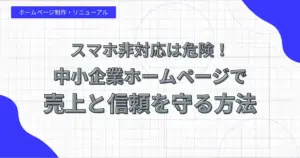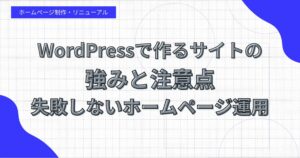「ホームページを新しく作りたいけれど、費用の相場がわからない」「予算をどう組めばいいのか不安」──こうした悩みは多くの中小企業が抱えています。制作会社の見積もりを受け取って初めて「こんなに費用がかかるのか」と驚くケースも少なくありません。ホームページは企業の顔ともいえる存在だからこそ、制作費用は慎重に考える必要があります。
この記事では、中小企業向けにホームページ制作費用の相場を整理しつつ、失敗しない予算の立て方を解説します。費用の内訳や注意すべきポイントを理解しておけば、安心して制作会社に相談できるはずです。
1. 中小企業向けホームページ制作費用の相場

ホームページ制作の費用は「サイトの規模」「デザインの自由度」「導入する機能」「依頼先の種類」によって大きく変動します。小規模な企業サイトと、EC機能を備えた大規模サイトでは、同じ「ホームページ制作」といっても金額感がまったく異なります。
- 小規模サイト(5〜10ページ、テンプレート中心):20万〜50万円
- 中規模サイト(10〜30ページ、オリジナルデザイン多め):50万〜150万円
- 大規模サイト(30ページ以上、EC・会員制機能あり):150万〜300万円以上
あくまで目安ですが、「ページ数や機能」「デザインの自由度」「CMSや運用方法」によって費用は大きく変動します。予算を考える際は、この幅を理解しておくことが大切です。
特にEC機能や予約システムなどの追加開発は費用を大きく押し上げる要因になります。「安い見積もりをもらったけど、あとからオプション追加で高額になった」という話も珍しくありません。
2.制作費用の内訳を知ろう

見積もりを受け取っても、「結局この金額は何にかかっているんだろう?」となんとなく腑に落ちないことはよくあります。ホームページ制作の費用は、ざっくり言えばいくつかの要素が積み重なって決まります。
- デザイン費(オリジナル or テンプレート)
- コーディング費(HTML/CSS/JavaScript実装)
- コンテンツ制作費(テキスト、写真、動画)
- システム・機能開発費(フォーム、EC機能、会員制など)
- サーバー・ドメイン費(維持費として毎年数千〜数万円)
例えば、オリジナルデザイン+EC機能付きで30ページのサイトを作る場合、デザイン・コーディングだけで100万円を超えることもあります。
デザインに力を入れるのか、テンプレートを使うのか、システムを組み込むのかによっても金額は変わってきます。大枠を知っておくだけでも、見積もりの妥当性を判断しやすくなるでしょう。
改善策
見積もりを受け取った際には、項目ごとに「これは何のための費用か」「どこまで含まれているか」を確認するのが安心です。同じ100万円でも、デザインに重きを置いているのか、システム開発に比重があるのかで意味が変わります。制作会社に聞けば大抵は説明してもらえるので、疑問点はそのままにせず整理しておくと、後々のトラブルを防げます。
3. 依頼前に準備しておくと費用を抑えられること
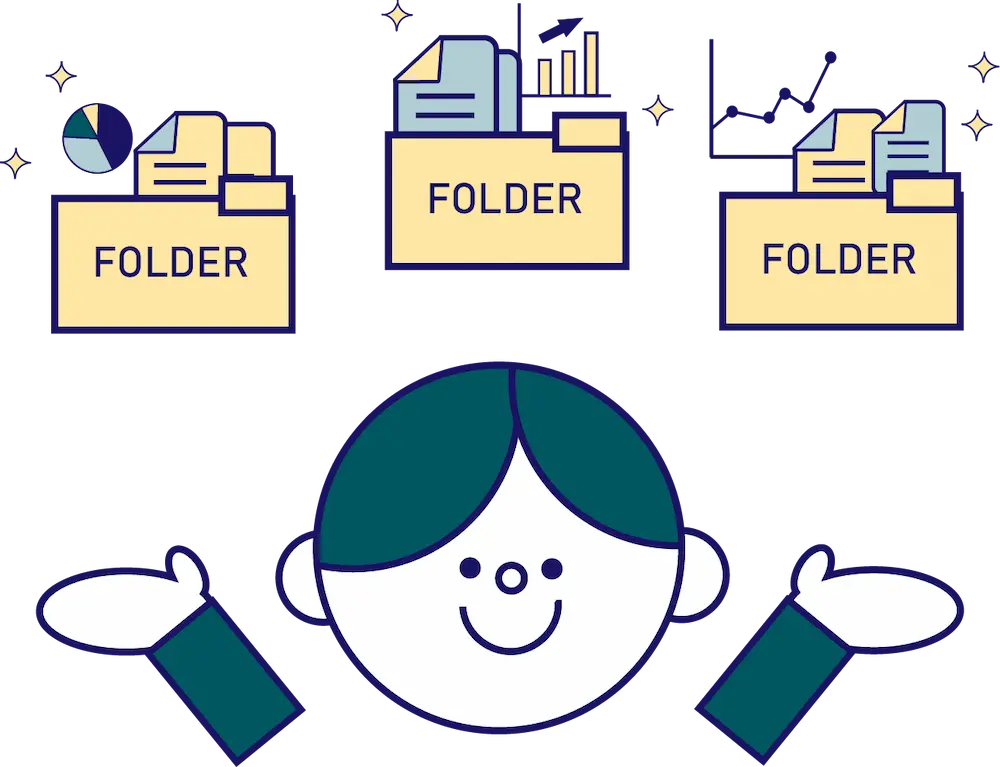
ホームページ制作はすべてを制作会社に任せることもできますが、依頼前に自社で準備しておくと費用を抑えられる部分も少なくありません。特に情報整理や素材の用意は、制作の効率化につながりやすく、見積もり金額にも影響してきます。
準備としては、こんなことを押さえておくと効果的です。
- 掲載ページやコンテンツのイメージを固める
- 既存素材(写真・ロゴ・文章)の整理。新規作成が減るほど費用が下がります。
- 優先したい機能や改善点の明確化。必要な機能を絞ることでコストを抑えられます。
- 参考にしたいサイトやデザインのイメージをまとめておく
改善策
最初から「必要なページ数」「必須の機能」「更新頻度」などを整理してから依頼すれば、見積もりの精度は格段に上がります。ざっくりした予算感だけで進めるのではなく、要件を具体化することが予算オーバーを防ぐ第一歩です。
4. デザインはテンプレートかオリジナルか

デザインの選択も費用に直結します。テンプレートを活用すれば安く仕上がりますが、オリジナリティに欠けることもあります。オリジナルデザインは自由度が高くブランドの印象を強められる一方、時間もコストもかかります。
- テンプレート:低コスト・短期間で制作可能ですが、デザインの自由度は低めです。
- オリジナルデザイン:費用高め・制作期間長めですが、ブランド価値の向上に効果的です。
改善策
中小企業の場合、テンプレートをベースにしながら必要な部分だけオリジナル要素を加えるのがバランスの良い選択肢です。全てをフルオーダーにせず、必要な箇所をカスタマイズすることで、費用を抑えつつ差別化も可能になります。
5. CMSを導入して更新コストを抑える
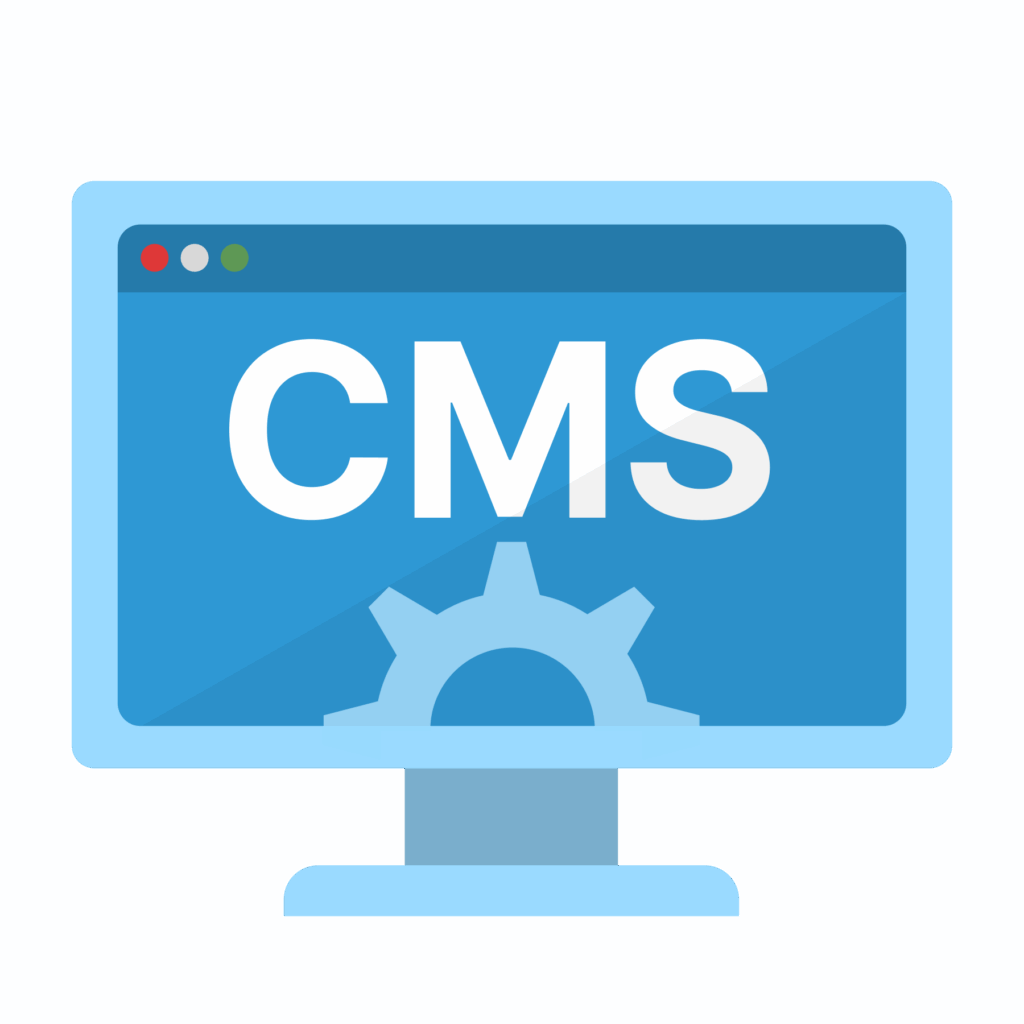
制作段階では見えにくいのが「更新コスト」です。制作会社に依頼しなければ更新できない構成だと、修正のたびに外注費がかかります。更新が滞れば、情報が古いまま放置されるリスクもあります。
改善策
WordPressやShopifyなどCMSを導入すれば、自社で情報更新が可能になります。担当者が簡単にブログ記事やニュースを追加できれば、運用コストを抑えつつ最新情報を発信できます。長期的に見れば大きな節約につながります。
CMS導入のメリット:
- テキストや画像の更新が自社で可能。
- ブログやお知らせなどの更新も簡単に行えます。
- プラグインや拡張機能で機能追加も楽になります。
- 運用効率が上がり、外注費を節約できます。
6. 追加機能は計画的に導入する
問い合わせフォーム、予約機能、ECなど、機能を盛り込みすぎると費用が一気に跳ね上がります。特に後から追加すると、仕様変更や再構築が必要になり、余計にコストがかかることも。
- 問い合わせフォーム:簡単なものは無料・低コストですが、高度な条件分岐や自動返信機能は追加費用が発生します。業種や運用目的に合わせて選ぶことが大切です。
- 予約システム:業種によっては必須で、導入費用と月額費用がかかる場合があります。
- EC機能:商品登録や決済機能の有無で費用が大きく変わります。
- 会員制機能:会員向けコンテンツ提供には開発費が必要です。
改善策
「今すぐ必要な機能」と「将来的に導入したい機能」を分けて考えましょう。初期費用を抑えたい場合は、最低限必要な機能だけに絞り込み、追加は段階的に検討するのが得策です。
7. 制作後にかかる運用・保守費用も忘れずに
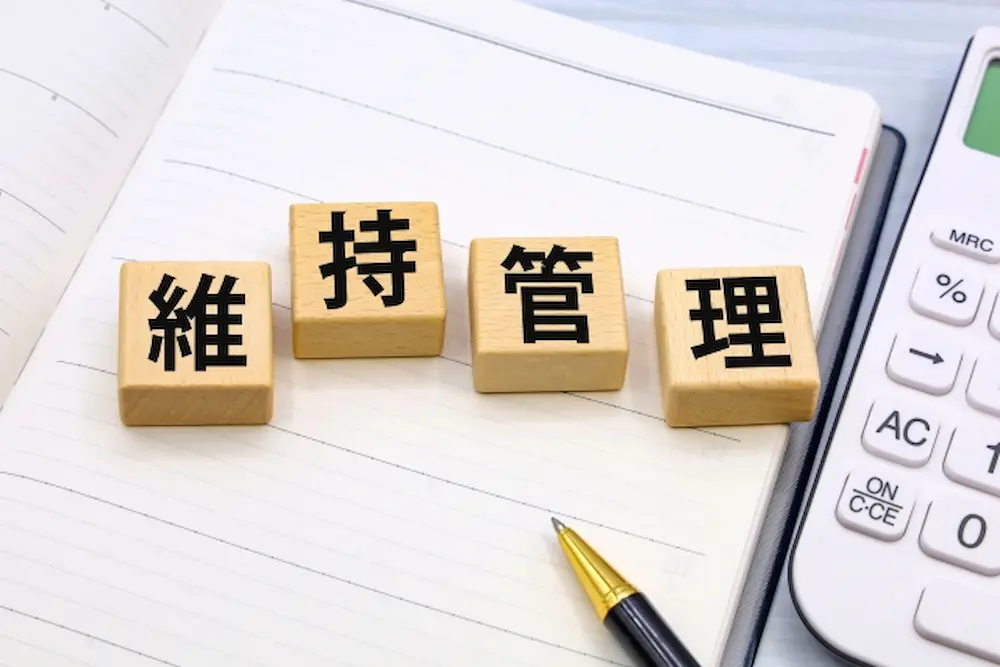
ホームページは公開して終わりではありません。公開後も、サーバー費用やドメイン更新料、SSL証明書の更新、CMSやプラグインのバージョンアップ、システムの保守・セキュリティ対策など、さまざまな運用コストが毎年発生します。制作費だけに目を向けてしまうと、この部分を見落とし、実際には想定以上の費用がかかってしまうこともあります。
また、運用コストの中には「更新のしやすさ」にも差があります。CMSを導入していない場合は、文章や画像の更新だけでも制作会社に依頼する必要があり、その都度費用が発生します。逆にCMSを導入していれば、自社で更新できるため、長期的な費用を大幅に削減できます。
改善策
制作会社に見積もりを依頼する際は、運用・保守費用についても必ず確認しましょう。。例えば「公開後1年間のサポート範囲」「月額いくらでどこまで対応してくれるか」「緊急時の対応は可能か」などです。これを把握しておくことで、後から追加費用が発生するリスクを減らせます。
8. 見積もりでチェックするポイント
見積もりをただ受け取るだけでは、必要な費用や追加費用の有無が不明確になりやすいです。チェックするポイントを押さえておくことで、後から「予算オーバー」のトラブルを防げます。
- 制作範囲が明確になっているか(ページ数・コンテンツ・機能)
- 追加費用の発生条件が明記されているか
- 保守・運用サポートの有無や費用が明確か
- 納期と支払い条件が具体的か
- 過去の制作事例や実績が確認できるか
まとめ:安心してホームページ制作に取り組むために
中小企業のホームページ制作は、費用感を把握し、内訳を理解したうえで予算を立てることが成功の鍵です。ポイントを整理すると以下の通りです。
- 制作範囲と必要ページ・コンテンツを明確にする
- デザインの自由度と費用を天秤にかける
- CMSや機能の優先順位を整理する
- 見積もりの内訳を確認し、追加費用の条件も把握する
- 長期的な費用対効果を意識する
ホームページ制作の費用は一律ではなく、要件によって大きく変わります。相場や内訳を理解し、必要な準備を整えてから依頼すれば、無駄なコストを減らせます。大切なのは「作って終わり」ではなく「運用まで見据えた予算設計」をすることです。
ホームページリニューアル.comでは、中小企業向けのホームページ改善・リニューアルに関して、契約不要の無料相談を受け付けています。
まずはご相談いただき、現状を整理するところから始めてみてください。もちろん相談だけでも構いませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
\ 話を聞くだけでもOK。無理な勧誘はありません。 /